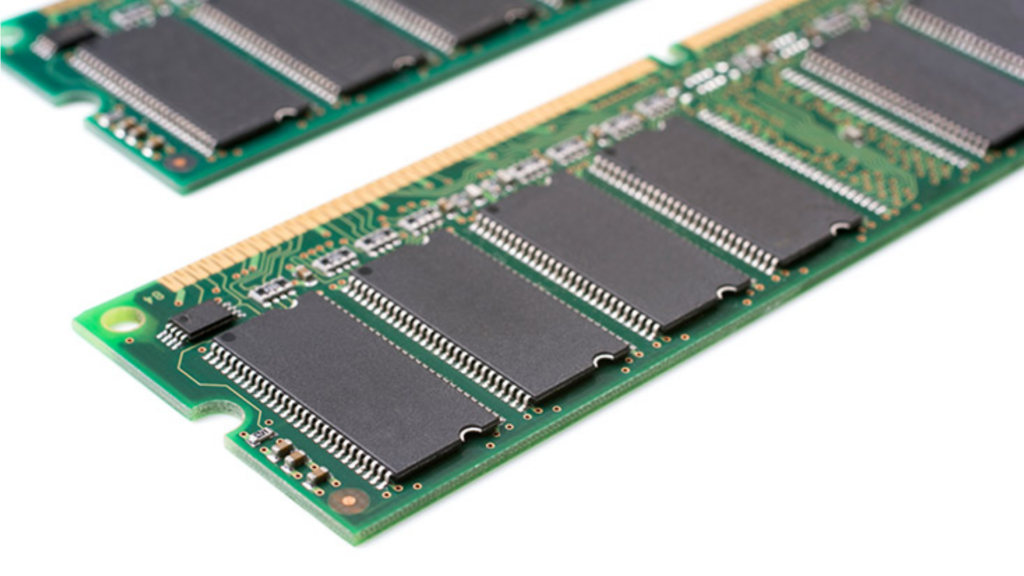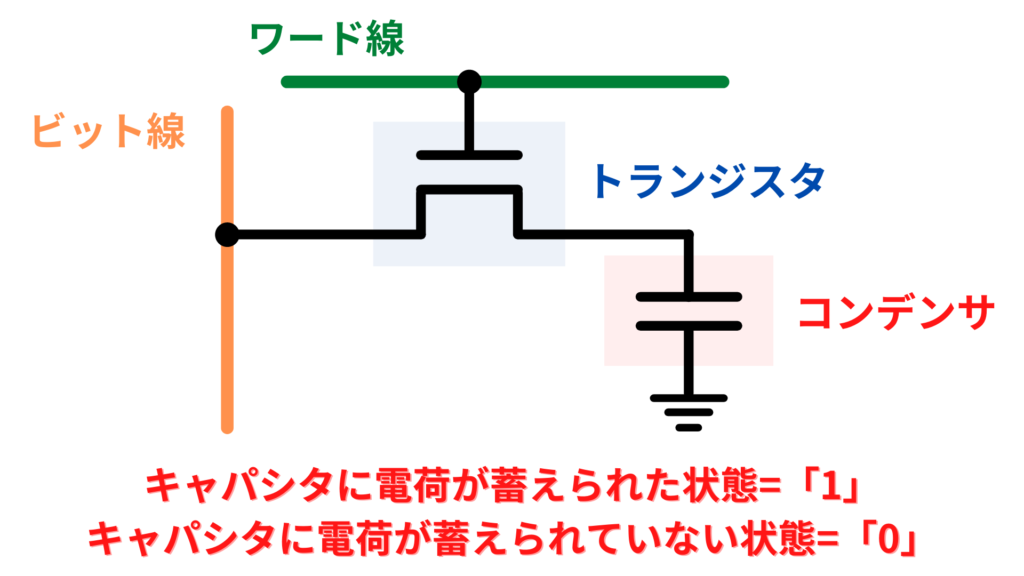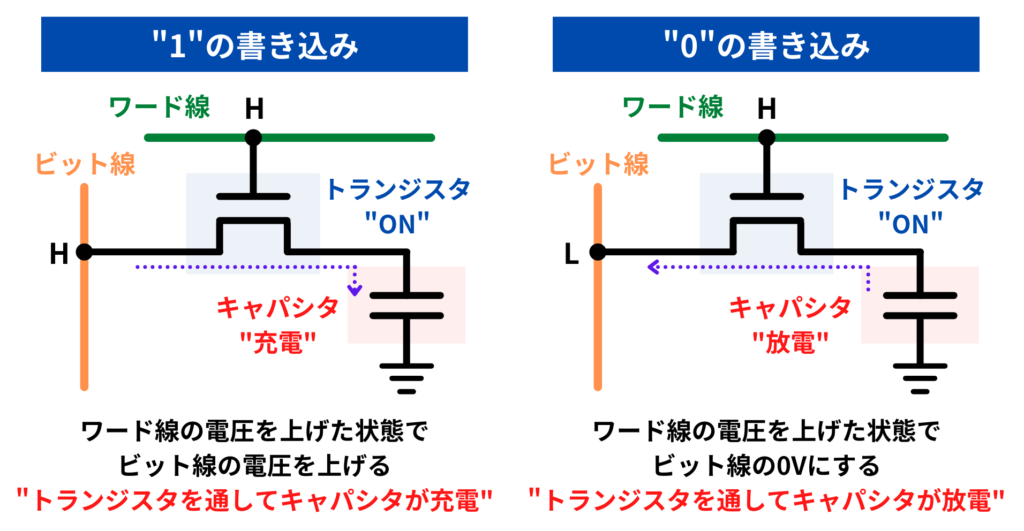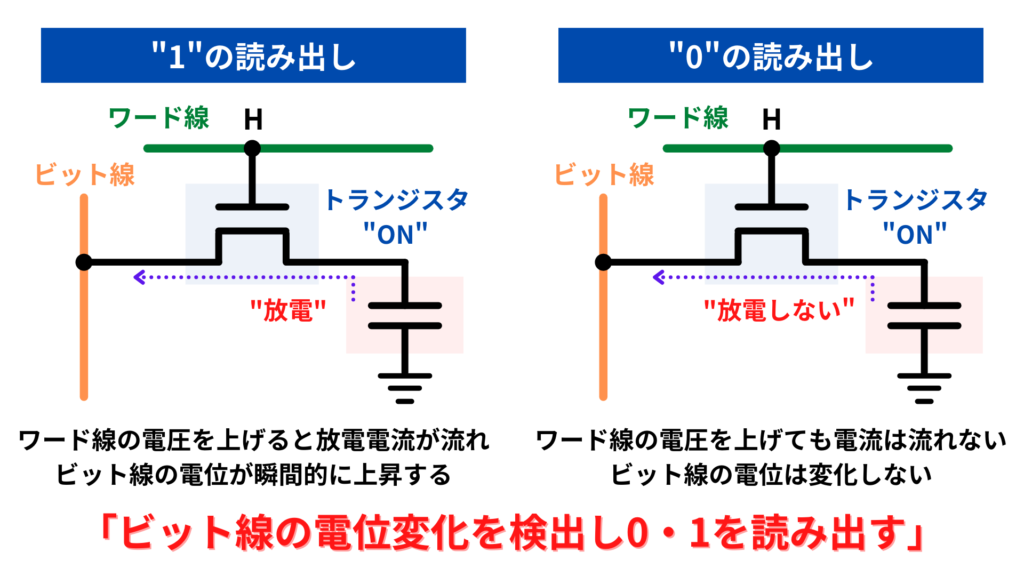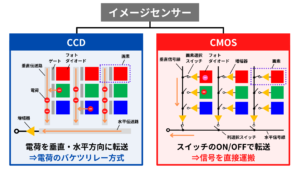DRAMとは:構造と動作原理
DRAMとは
DRAM(Dynamic Random Access Memory)は「コンデンサとトランジスタを組み合わせた揮発性メモリ(RAM)」です。
安価・大容量であることから、パソコンのメインメモリなど広く使用されています。
DRAMの回路構造
DRAMのメモリセル(0/1を記憶する最小単位)は「1個のトランジスタ(MOSFET)と1個のコンデンサ(キャパシタ)」から構成されています。
- トランジスタのゲートはワード線に接続
- トランジスタとキャパシタは直列で接続、トランジスタのソースはビット線に接続
ワード線の電位でトランジスタのON/OFFを制御
ビット線の電位によりキャパシタの充放電を制御
DRAMではキャパシタに電荷が蓄えられている状態を「1」、溜まっていない状態を「0」としてデータを記録しています。
なお、ワード線は行方向に走っており、メモリセルを選ぶための線です。ビット線は列方向に走っていて、データの読み書きに使われます。
DRAMの動作原理
DRAMの動作には以下の2つがあります。
- 書き込み:キャパシタに0・1を書き込む
- 読み出し:キャパシタに書き込まれたデータを読み出す
それぞれの動作原理を解説します。
書き込み動作の原理
簡略化の為ワード線・ビット線の電位が高い状態を「H(high)」、低い状態を「L(Low)」と記述します。
- 1の書き込み
- 0の書き込み
ワード線の電圧を上げた状態で、ビット線の電圧を上げる。トランジスタがONとなり、キャパシタが充電される
ワード線の電圧を上げた状態で、ビット線の電圧を0にする。トランジスタがONとなり、キャパシタがビット線に放電される
DRAMでは、トランジスタONの状態でビット線の電圧を調整し、キャパシタを充放電することで書き込みを行います。
読み出し動作の原理
- 1の読み出し
- 0の読み出し
ワード線の電圧を上げ、トランジスタをON。ビット線の電位が瞬間的に上昇する。
ワード線の電圧を上げ、トランジスタをON。ビット線の電位は変化しない。
DRAMは、トランジスタをONとしビット線の電位変化を検出することで、メモリセルの0・1を読み取ります。
前の講座
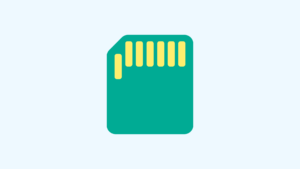
フラッシュメモリの構造と動作原理
次の講座

SRAMの構造と動作原理